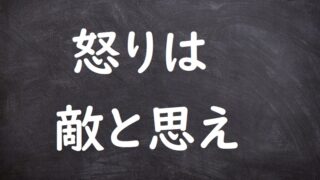 「い」
「い」 怒りは敵と思え(いかりはてきとおもえ)
分類ことわざ意味すぐ立腹し怒るのは、人の反感を買い、自分を破滅させる敵と考えて慎め、という戒め。何事を行う場合にも短気は損をする。怒りは自分を滅ぼす敵だから用心せよ、という意味。徳川家康の遺訓。同類語・同義語 短気は損気
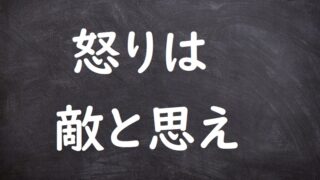 「い」
「い」 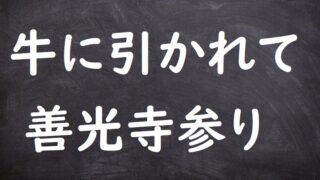 「う」
「う」 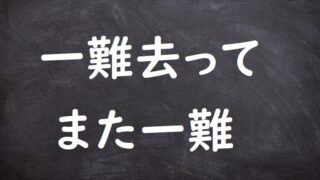 「い」
「い」 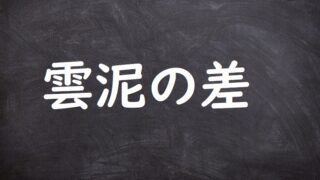 「う」
「う」 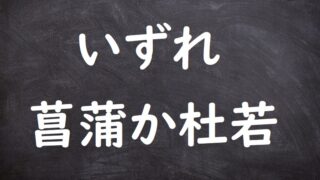 「い」
「い」 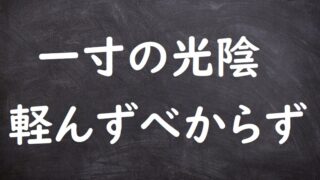 「い」
「い」 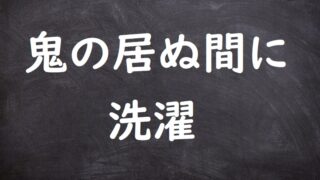 「お」
「お」 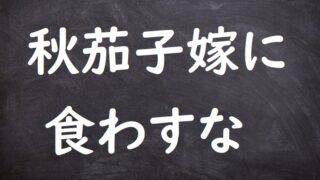 「あ」
「あ」 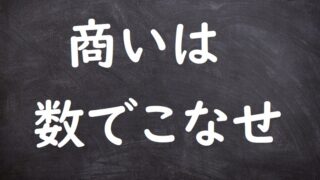 「あ」
「あ」 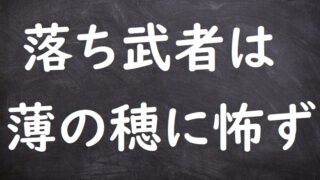 「お」
「お」 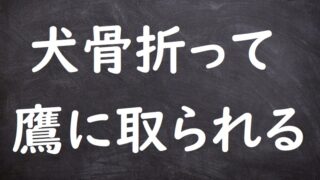 「い」
「い」 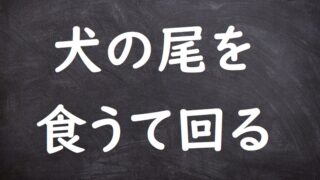 「い」
「い」 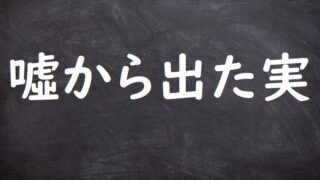 「う」
「う」 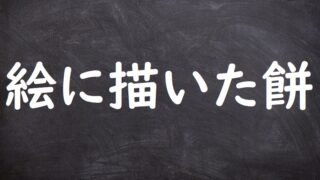 「え」
「え」 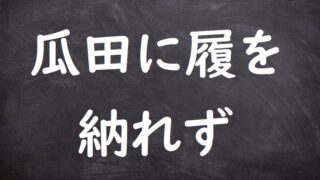 「う」
「う」 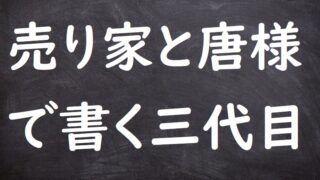 「う」
「う」 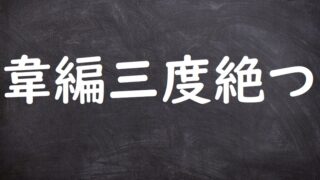 「い」
「い」 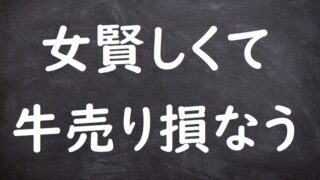 「お」
「お」 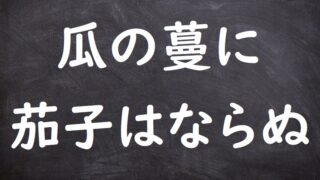 「う」
「う」 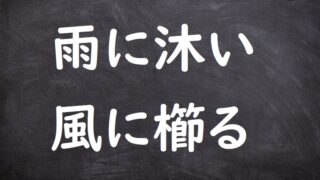 「あ」
「あ」