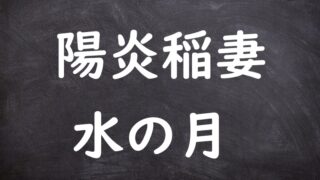 「か」
「か」 陽炎稲妻水の月(かげろういなずまみずのつき)
分類ことわざ意味とらえようのない様子のこと。 陽炎(かげろう)も、稲妻(雷)も、また、水に映った月も、あるかと思えばなかったり、ないかと思えばあったりと、そのようなとらえようのない様をたとえた言葉。
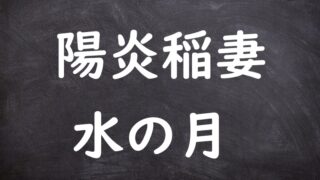 「か」
「か」 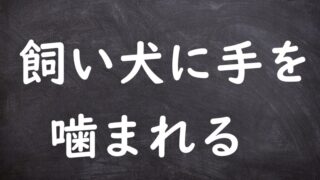 「か」
「か」 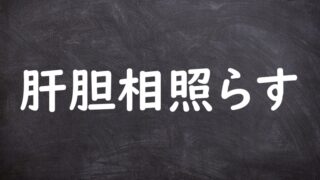 「か」
「か」 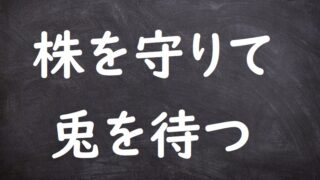 「か」
「か」 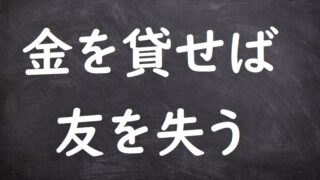 「か」
「か」 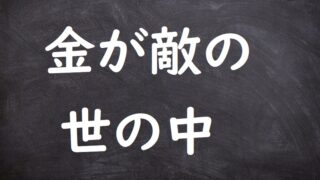 「か」
「か」 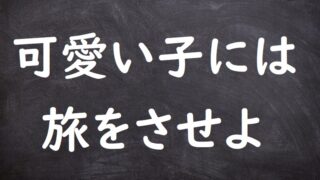 「か」
「か」 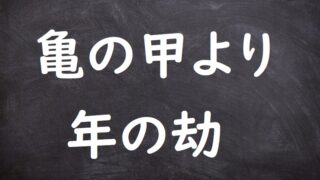 「か」
「か」 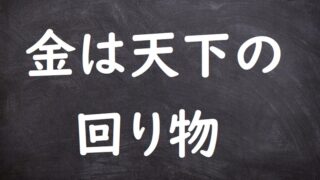 「か」
「か」 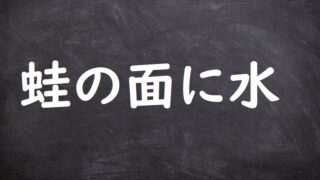 「か」
「か」 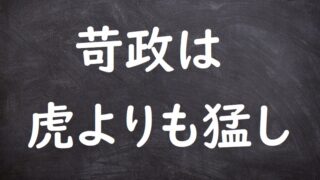 「か」
「か」 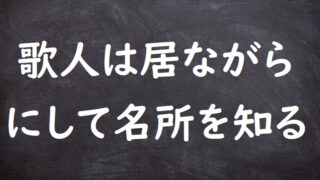 「か」
「か」 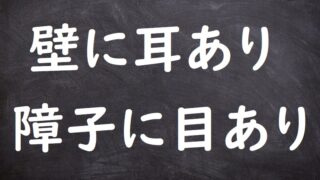 「か」
「か」 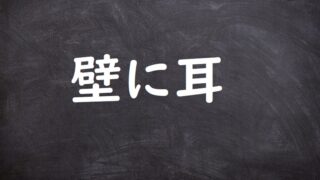 「か」
「か」 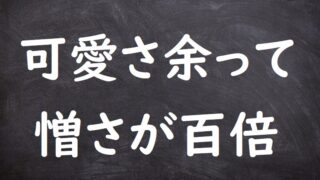 「か」
「か」 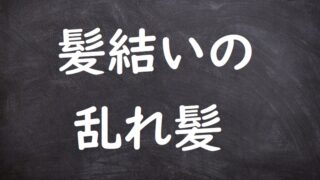 「か」
「か」 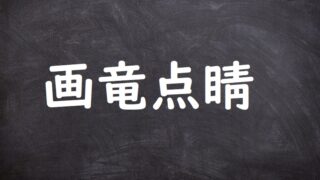 「か」
「か」 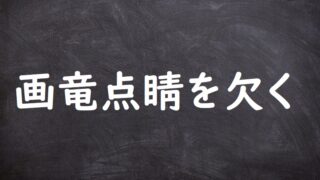 「か」
「か」 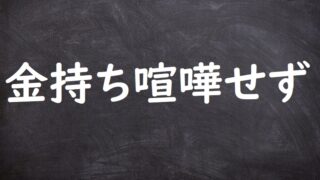 「か」
「か」 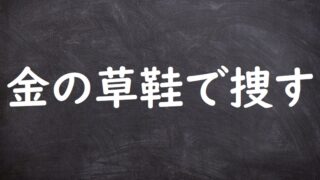 「か」
「か」