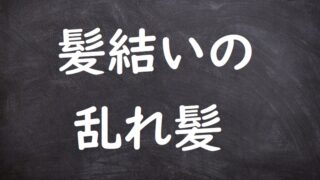 「か」
「か」 髪結いの乱れ髪(かみゆいのみだれがみ)
分類ことわざ意味自分自身の仕事が他人だけに向けられ、自分にまでは手が回らないことをいう。髪結いさん(美容師)が、自分の髪は乱れているということから。同類語・同義語 紺屋の白袴(こうやのしろばかま) 医者の不養生(いしゃのふようじょう) 坊主...
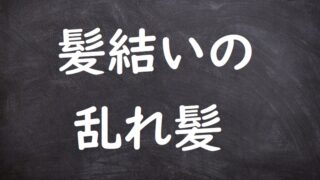 「か」
「か」 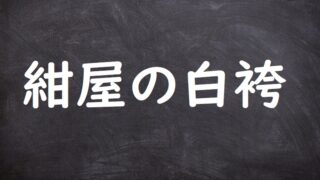 「こ」
「こ」 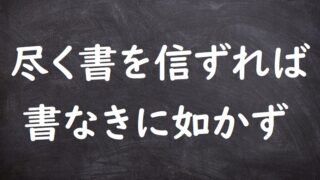 「こ」
「こ」 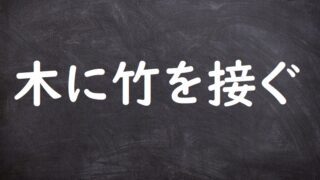 「き」
「き」 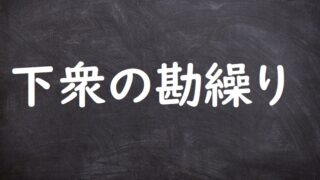 「け」
「け」 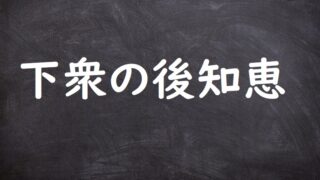 「け」
「け」 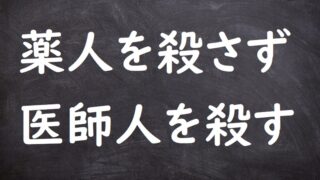 「く」
「く」 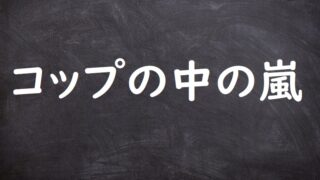 「こ」
「こ」 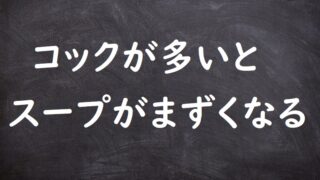 「こ」
「こ」 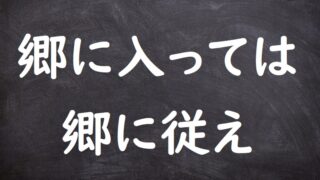 「こ」
「こ」 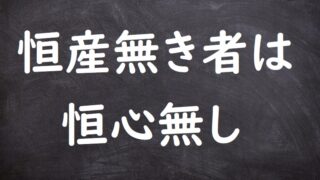 「こ」
「こ」 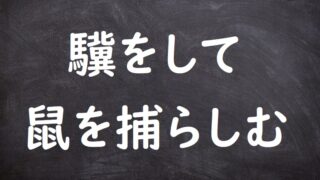 「き」
「き」 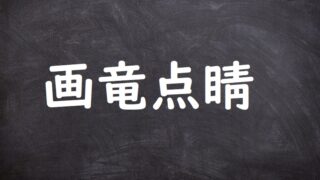 「か」
「か」 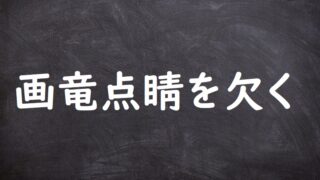 「か」
「か」 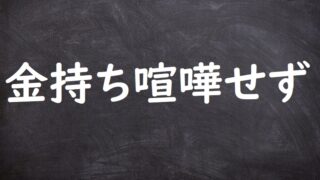 「か」
「か」 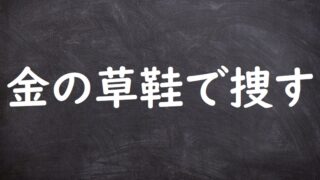 「か」
「か」 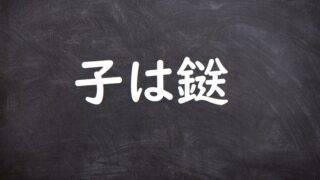 「こ」
「こ」 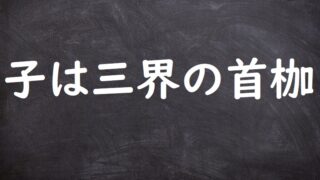 「こ」
「こ」 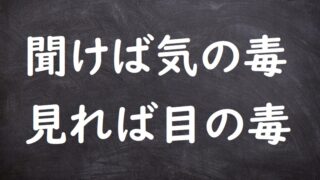 「き」
「き」 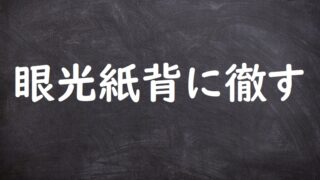 「か」
「か」