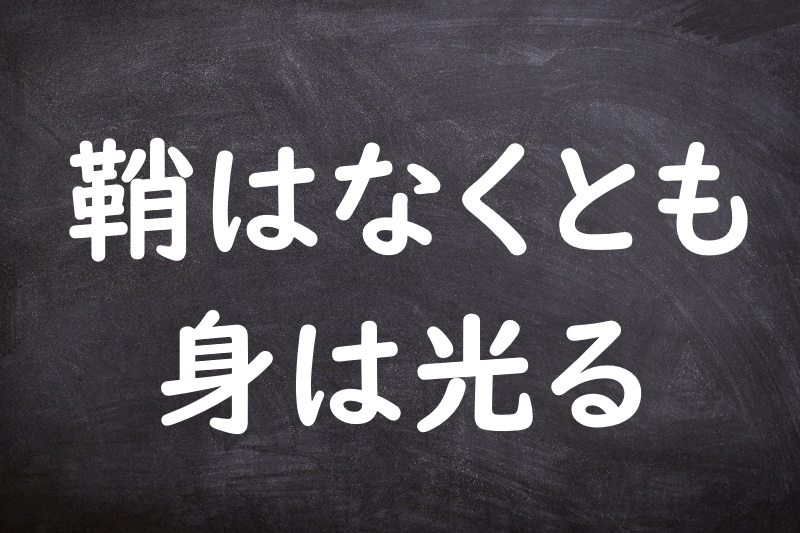 「さ」
「さ」 鞘はなくとも身は光る(さやはなくともみはひかる)
分類ことわざ意味問題は形ではなく中身である、という意味。刀は鞘に入っているものであるには違いないが、鞘が無くとも刀の光具合に変わりはない、ということから。同類語・同義語杓子を定規にする(しゃくしをじょうぎにする)
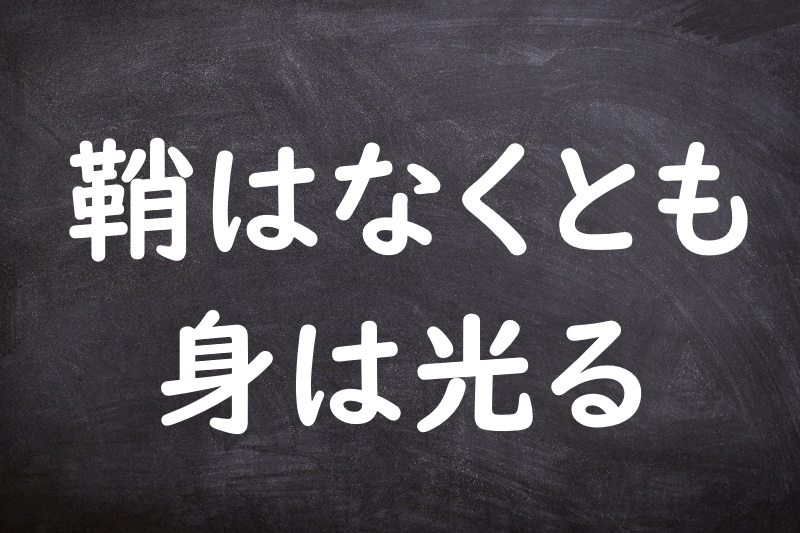 「さ」
「さ」 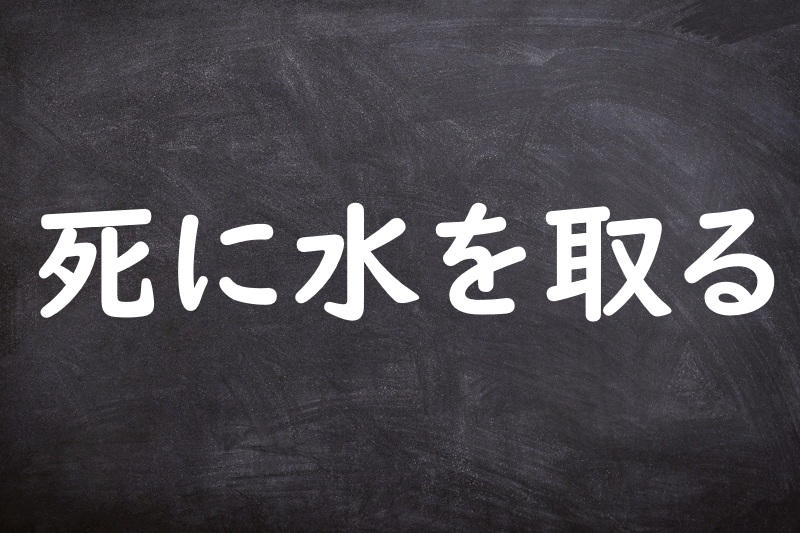 「し」
「し」 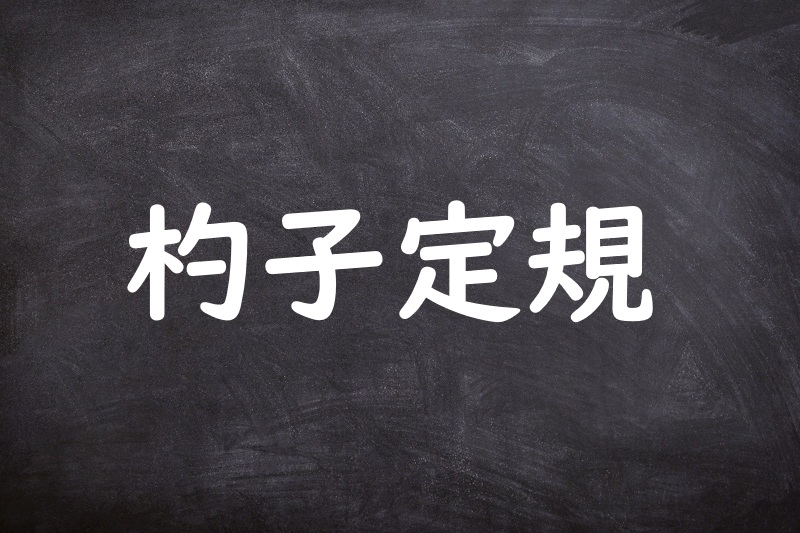 「し」
「し」 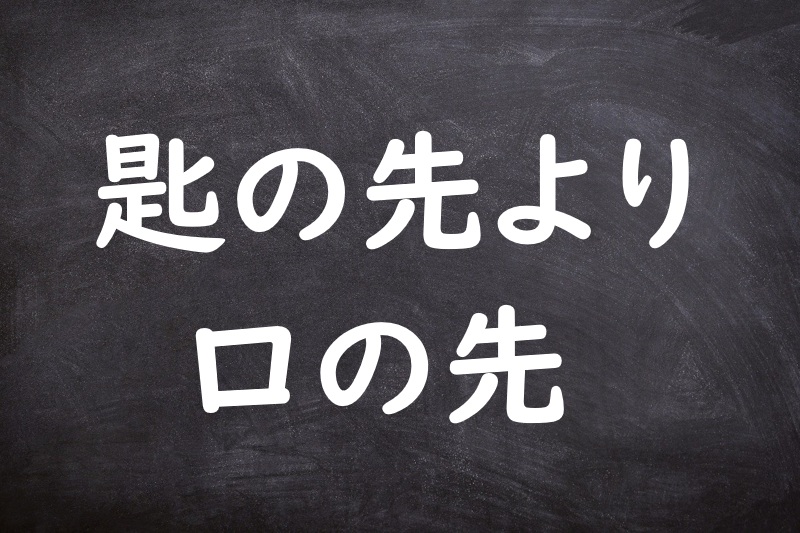 「さ」
「さ」 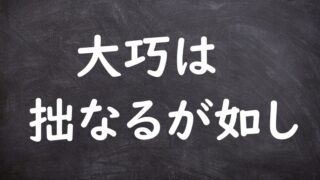 「た」
「た」 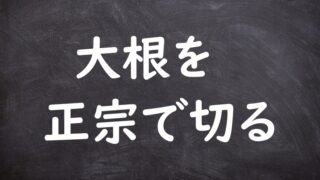 「た」
「た」 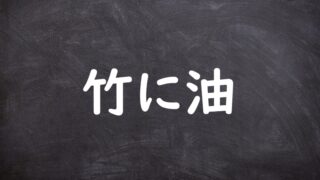 「た」
「た」 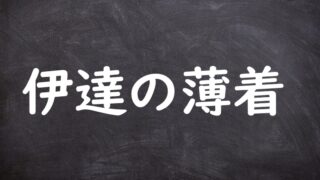 「た」
「た」 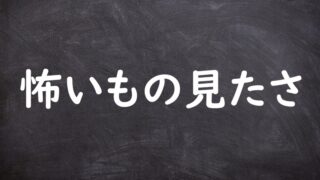 「こ」
「こ」 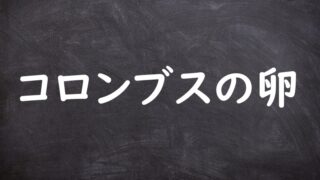 「こ」
「こ」 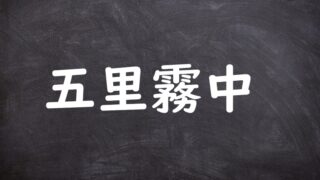 「こ」
「こ」 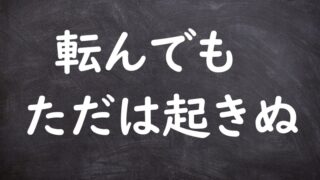 「こ」
「こ」 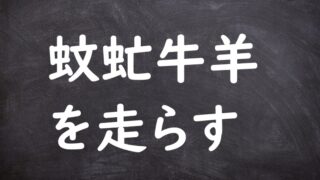 「ふ」
「ふ」 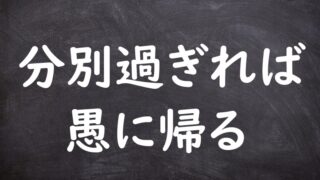 「ふ」
「ふ」 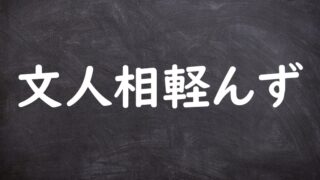 「ふ」
「ふ」 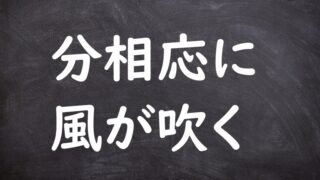 「ふ」
「ふ」 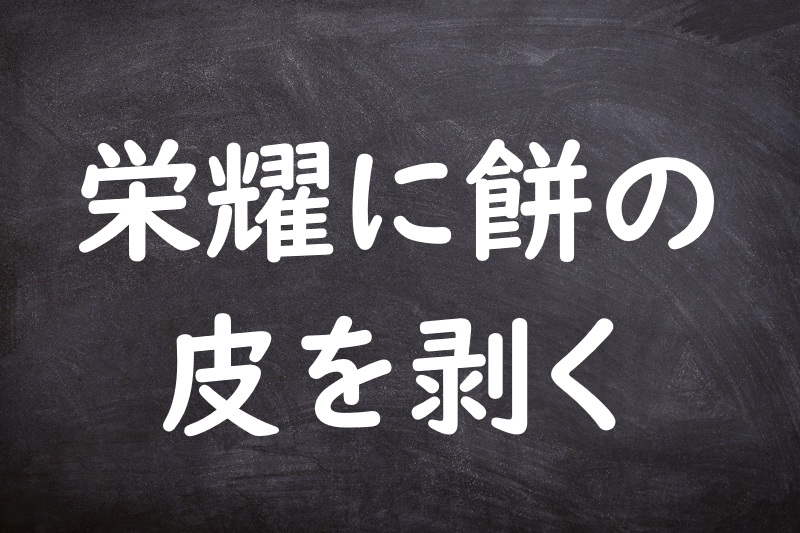 「え」
「え」 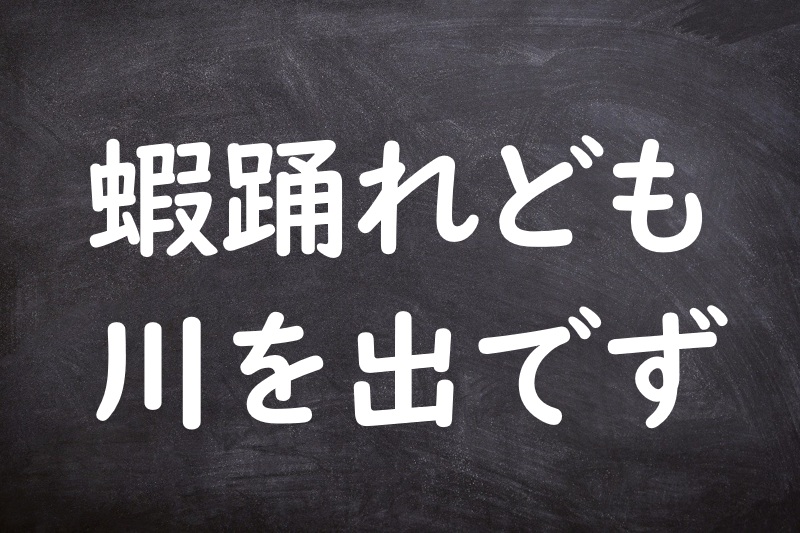 「え」
「え」 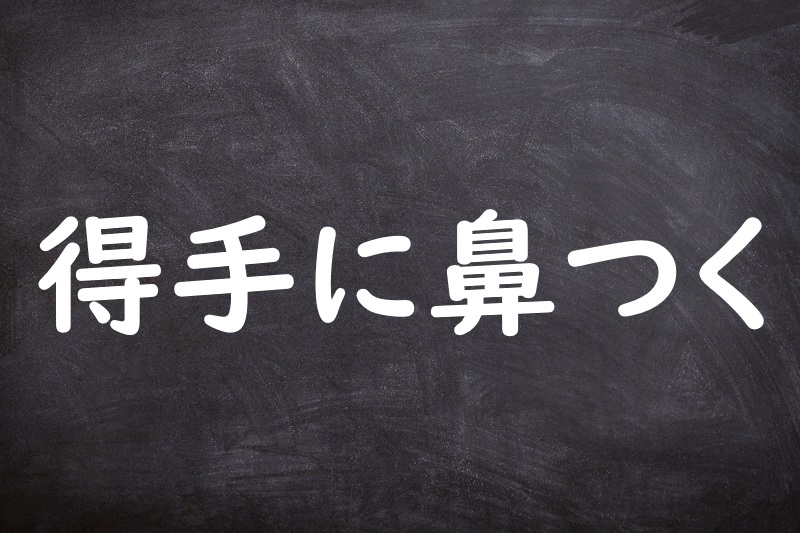 「え」
「え」 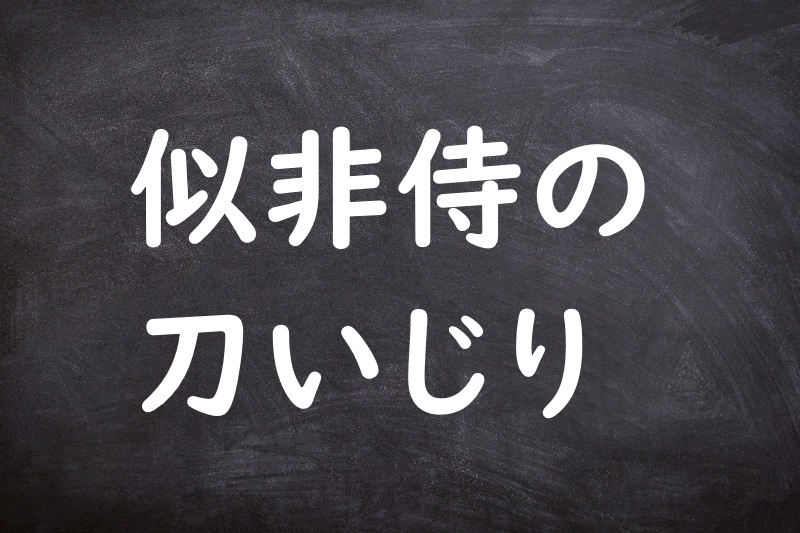 「え」
「え」