ことわざ・格言・故事のなかで、「自然」に関するもの、「自然」のフレーズが入ってるものをピックアップしています。
自然
 自然
自然  自然
自然 ことわざ・格言・故事のなかで、「自然」に関するもの、「自然」のフレーズが入ってるものをピックアップしています。
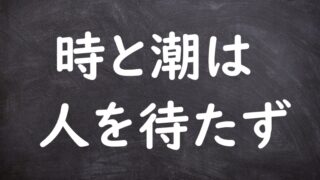 「と」
「と」 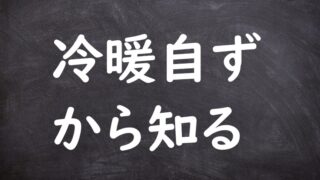 「れ」
「れ」 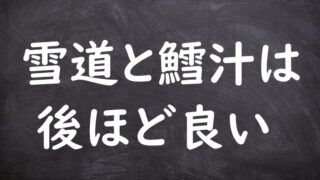 「ゆ」
「ゆ」 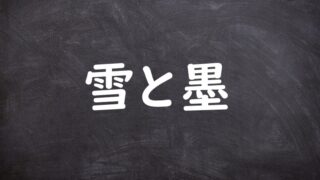 「ゆ」
「ゆ」 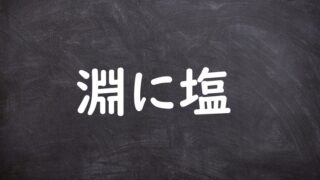 「ふ」
「ふ」 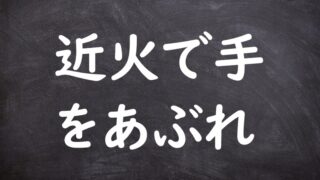 「ち」
「ち」 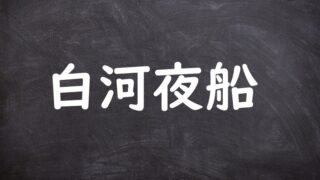 「し」
「し」 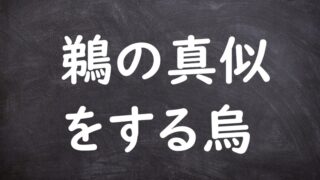 「う」
「う」 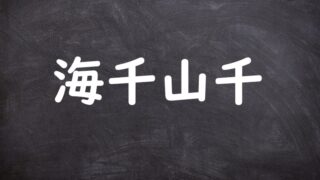 「う」
「う」 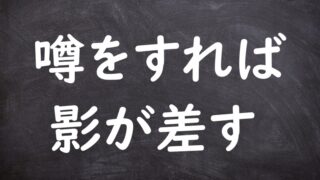 「う」
「う」 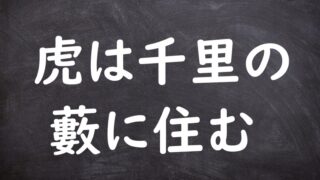 「と」
「と」 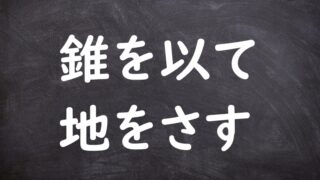 「き」
「き」 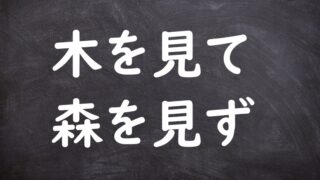 「き」
「き」 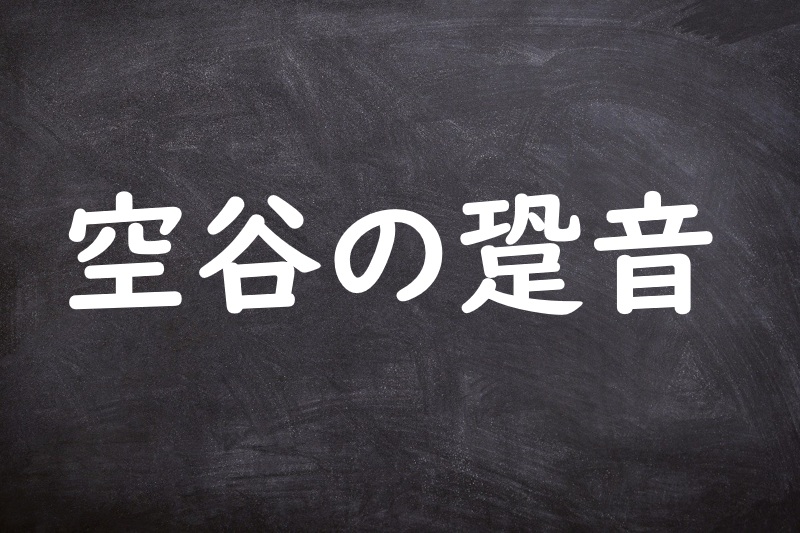 「く」
「く」 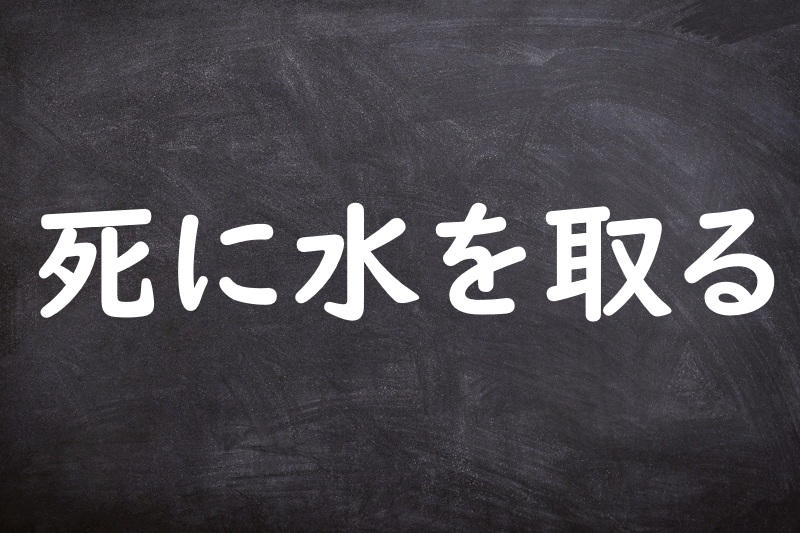 「し」
「し」 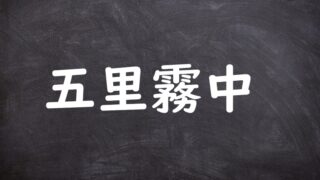 「こ」
「こ」 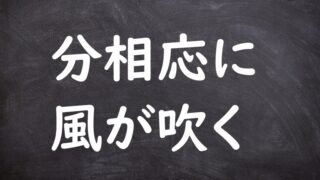 「ふ」
「ふ」 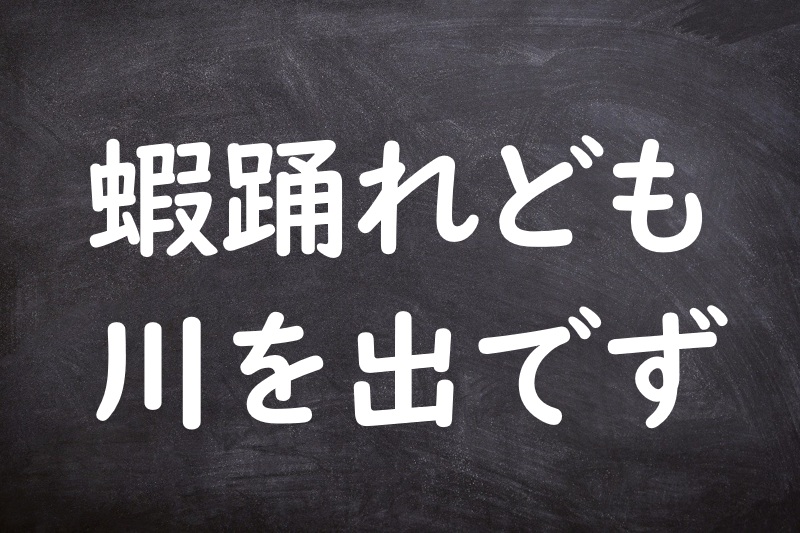 「え」
「え」 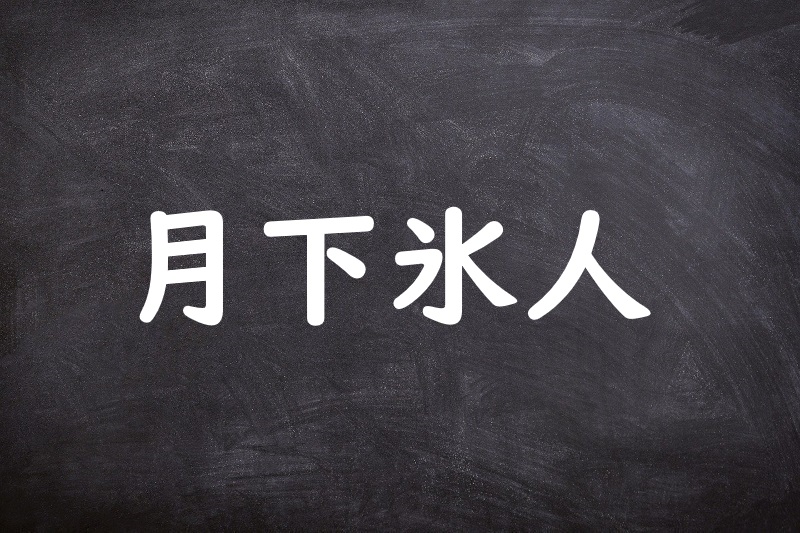 「け」
「け」 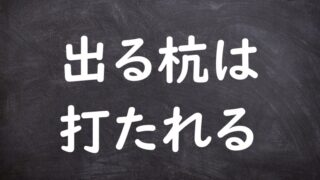 「て」
「て」