ことわざ・格言・故事のなかで、「道具」に関するもの、「道具」類のフレーズが入ってるものをピックアップしています。
道具
 道具
道具  道具
道具 ことわざ・格言・故事のなかで、「道具」に関するもの、「道具」類のフレーズが入ってるものをピックアップしています。
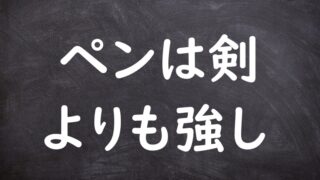 「へ」
「へ」 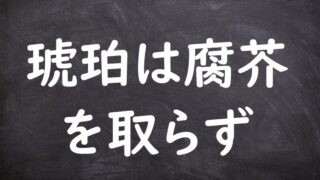 「こ」
「こ」 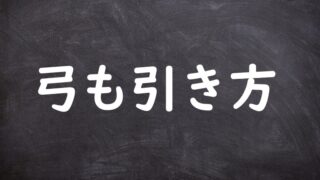 「ゆ」
「ゆ」 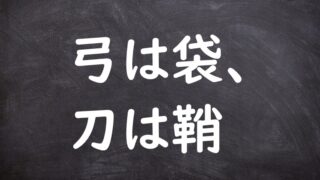 「ゆ」
「ゆ」 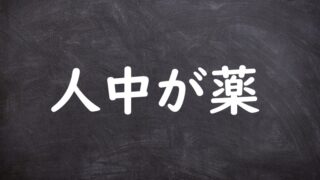 「ひ」
「ひ」 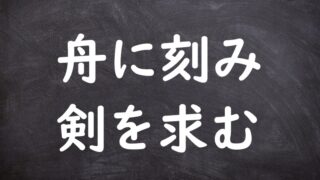 「ふ」
「ふ」 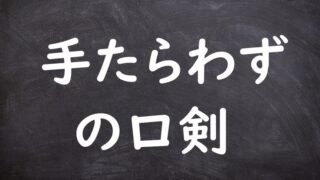 「て」
「て」 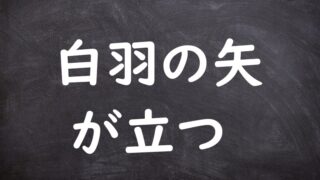 「し」
「し」 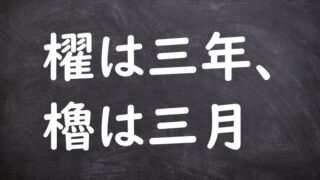 「か」
「か」 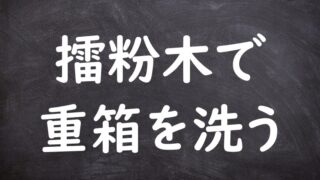 「す」
「す」 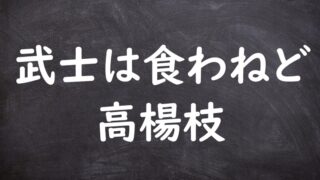 「ふ」
「ふ」 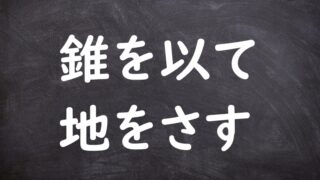 「き」
「き」 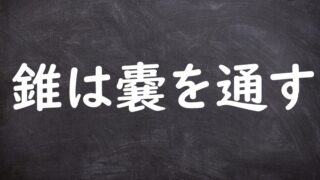 「き」
「き」 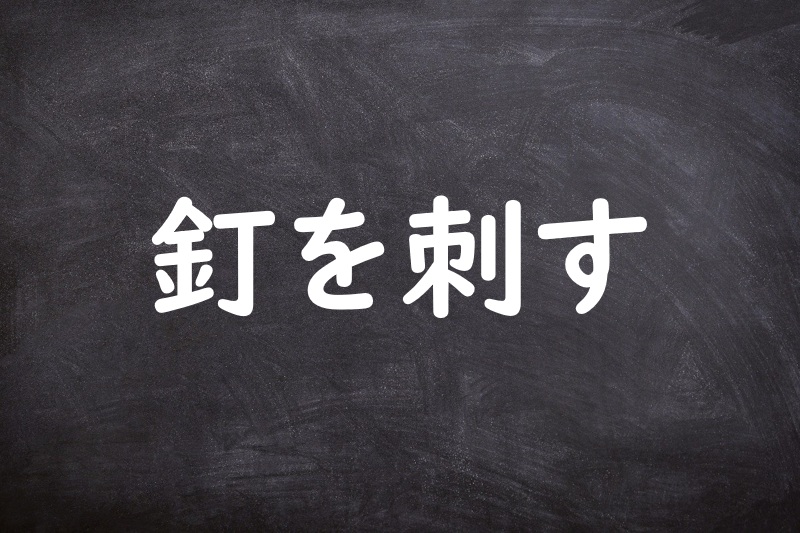 「く」
「く」 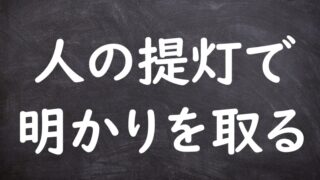 「ひ」
「ひ」 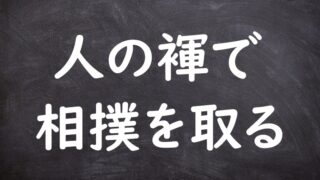 「ひ」
「ひ」 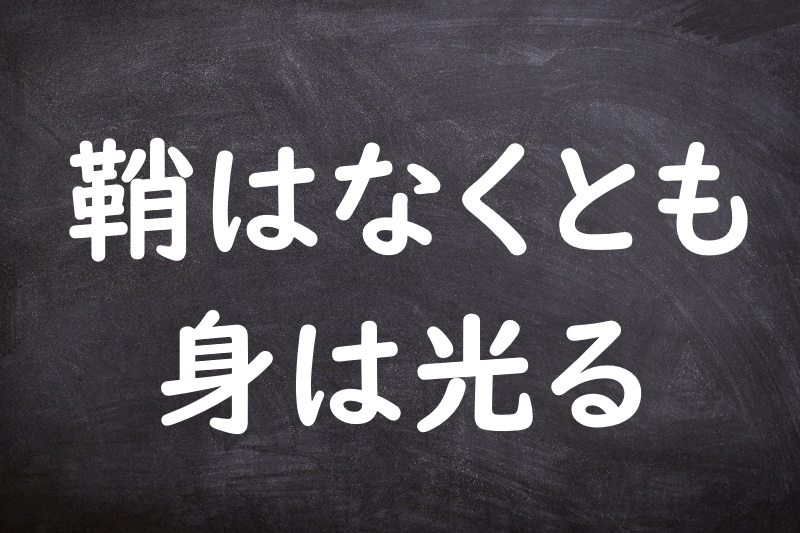 「さ」
「さ」 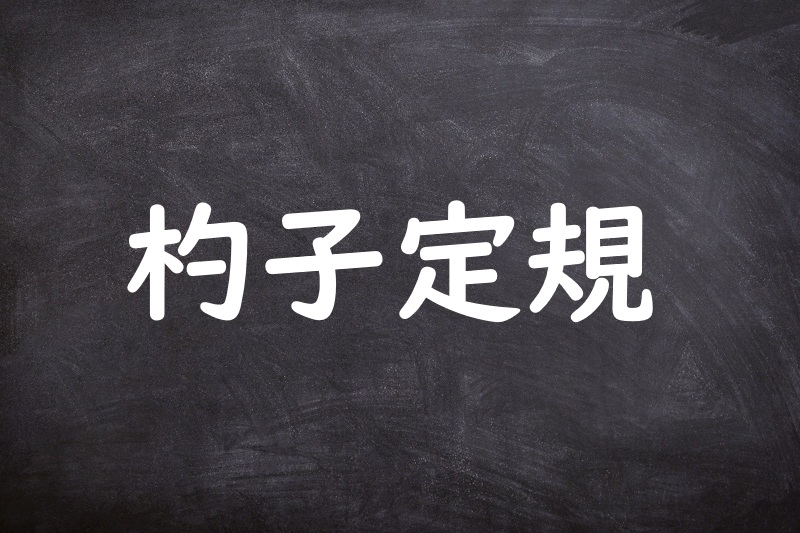 「し」
「し」 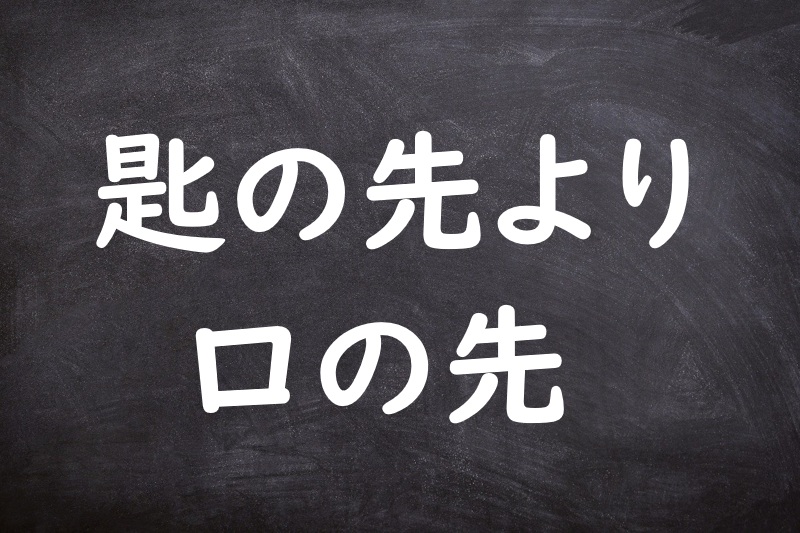 「さ」
「さ」 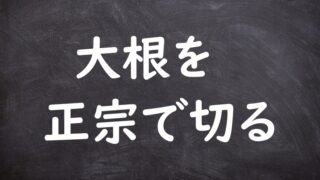 「た」
「た」