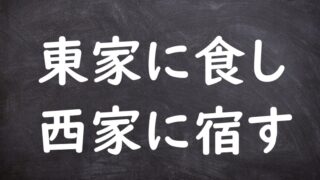 「と」
「と」 東家に食し西家に宿す(とうけにしょくしせいかにしゅくす)
分類ことわざ意味二つの良いことを同時に得ようとすることをいう。
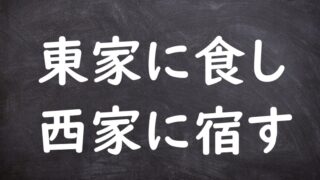 「と」
「と」 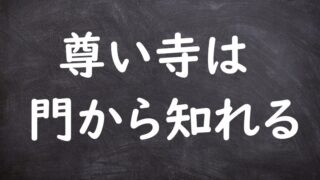 「と」
「と」 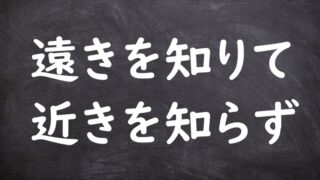 「と」
「と」 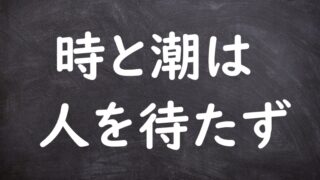 「と」
「と」  「た」
「た」 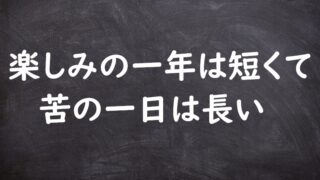 「た」
「た」 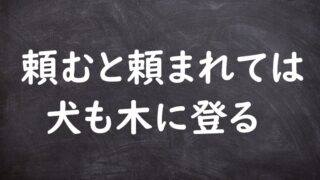 「た」
「た」 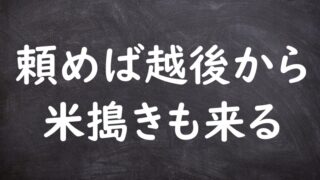 「た」
「た」 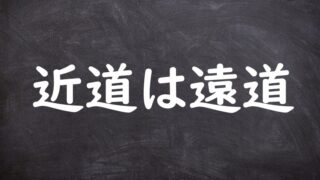 「ち」
「ち」 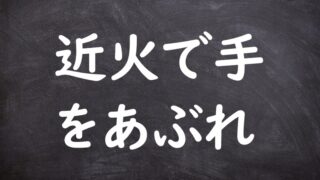 「ち」
「ち」 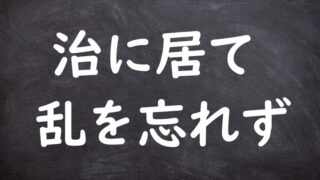 「ち」
「ち」 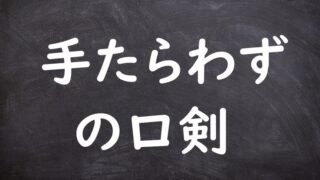 「て」
「て」 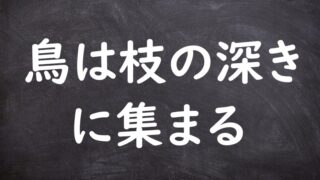 「と」
「と」 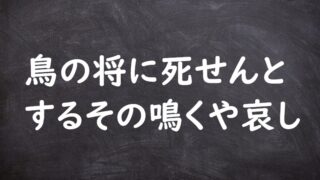 「と」
「と」 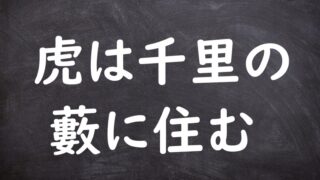 「と」
「と」 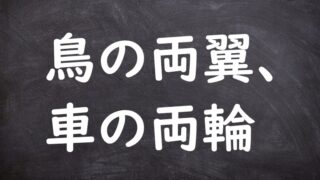 「と」
「と」 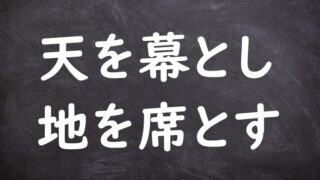 「て」
「て」 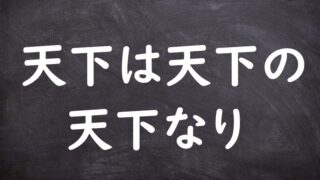 「て」
「て」 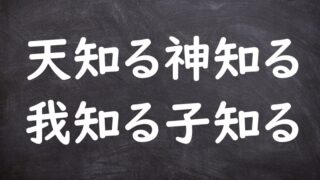 「て」
「て」 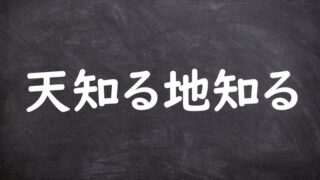 「て」
「て」